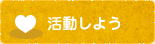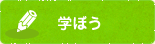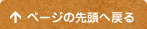- TOP
- 学ぼう
- 知る、感じる、考える
- さまよう若者
- 自死防止
- 生きやすい社会の実現をめざして―自殺予防の現在―
自死防止
生きやすい社会の実現をめざして―自殺予防の現在―
ぴっぱら2008年11月号掲載
「自分が母を死なせたという、ぬぐいきれない思いがある」と、青年は聴衆の前で語りました。第4回「世界自殺予防デーシンポジウム」の「自死遺族の体験談」でのことです。
現在、日本における自殺者は10年連続で年間3万人を越え、これは交通事故死者数のおよそ6倍です。またそれは、かけがえのない人を失い、悲しみにくれる遺族が、おおよそ毎年14万人以上増え続けていることを意味しています。
これまで、自殺を少しでもくいとめようと、各地で個人や民間の団体によるさまざまな取り組みが行われてきました。そうしたさなか、平成18年に「自殺対策基本法」が成立し、国を挙げて自殺対策に取り組む体制がようやく出来つつありますが、依然、自殺者が減るきざしは見えてきません。私たちはこの実態をどのように受け止めたらよいのでしょうか。そして、一人ひとりにいま何ができるのでしょうか。
◆自殺の実態を探る
去る9月14日、東京ビッグサイト国際会議場にて、自殺対策支援を行うNPO法人「ライフリンク」主催、内閣府と東京都共催のシンポジウムが開かれました。1000人収容の会場は多数の参加者で埋まり、自殺問題に対する関心の高さをうかがわせました。
4回目の開催を迎える今回は、「緊急報告『自殺実態白書』から見えてきたこと」と題し、ライフリンクをはじめとする、民間の有志で作るプロジェクトチームがまとめた自殺実態に関する報告書の内容を紹介、実効性のある対策を推進するための提言が行われました。
シンポジウムはライフリンクの代表を務める清水康之さんのあいさつに始まり、第1部に自死遺族の体験談、続く第2部では、『自殺実態白書』にもとづく報告が行われました。そして、第3部では識者や研究者、政府の対策関係者などによるパネルディスカッションが行われました。
◆自死遺族の苦しみ
第1部では、母の自死をきっかけに精神科医を目指し、現在は研修医となっている、28歳の藤本佳史さんが、自らの経験を語りました。
藤本さんは、大学生であった19歳のときに、買い物に出たわずかな間に母を亡くしました。それからはずっと、「なぜ母を救えなかったのだろう」という思いが消えず、苦しみ続ける毎日だったといいます。母を恋しいと思う気持ちと、「いったいどうして」という怒りの気持ちに押しつぶされそうになった藤本さんは、「あしなが育英会」の存在を知り、同じ思いを持つ大勢の仲間と話すことで、気持ちの整理ができてきたと語りました。
藤本さんの言葉で印象的だったのが、「かつて自分がそうだったように、苦しみを誰にも打ち明けられず、苦しんでいる遺族が世の中に大勢いる」ということです。自死遺族の多くは、死別そのものの苦しみに加え、隠すことの苦しみをも背負っているのです。
『白書』によると、身内の死について周囲から気になる発言をうけたことがあるという自死遺族は、全体の約6割にものぼるとされています。親戚や近所の人、時には家族までにも「一緒に住んでいたのに何で止められなかった」「(あなたの)育て方が間違っていた」「自殺なんて弱い人間のすることだ」などと責められたり、こころない発言にさらされたりする人が多数いるのです。
愛する人の死に対して、ほとんどの遺族は悲しみとともに強い罪責感を抱いているといいます。その上、さらに他人から偏見の目を向けられ、責められるというのは本当につらいことでしょう。自死遺族の4人に1人が「自分も死にたい」と考えたことがあるというデータも公表されています。藤本さんが語った「あしなが育英会」をはじめ、全国にはさまざまな自死遺族のつどい(自助グループ)が存在します。今年の1月には、そうした遺族支援に取り組む団体をサポートする、「全国自死遺族総合支援センター」が東京都で発足しました。同センターは、遺族支援に取り組む各地の専門家や団体同士をネットワークでつなぎ、それぞれの専門知識やノウハウを持ち寄るといい、さらなる手厚い支援態勢づくりが期待されています。
自死遺族の言葉は、経験者の貴重な「声」として自殺防止の大きな力となっています。遺族が安心して思いを語れる場所を提供し、心理的、経済的なケアを行っていくとともに、自殺で亡くなる人が一人でも少なくなるよう、その声を取り組みに確実に反映させていくことが大切なのです。
自死遺族が自らの体験を語ることは、はかりしれない苦しみと葛藤を乗り越えた末のことであるということを、私たちは胸に刻んでおく必要があるのではないでしょうか。
◆必要なところに、適切な支援を
第2部では『白書』にもとづき調査結果の報告が行われ、現行の自殺対策最大の問題点として、対策が総花的で優先順位がつけられていないこと、また、情報や支援策が当事者のために一元化されていないことが挙げられました。
つまり、自殺防止の取り組みを行おうにも、それぞれ地域別の分析が不十分なため、どの地域でも同じような「啓発中心の支援」に偏りやすい。その結果として、当事者や家族がどこかに助けを求めても、適切なケアをする機関にまではなかなかたどり着かず、救い出せないケースにつながっているという現実が存在しているのです。
それを改善するための問題点として『白書』では、地域によって自殺者の年代・性別・雇用状況別の「自殺のハイリスク群」が異なることを明らかにしました。つまり、たとえ同じ県内であっても、自殺者が被雇用者の若い年代に集中している地域と、無職の老年世代に集中しているところとでは、同じ対策を実行しようとしても大きな効果をあげるのは難しいということです。
そこで、調査によって明らかになったさまざまなデータを洗い出し、ハイリスク群を特定していくことによって、その人たちに接する機会のある行政の窓口に働きかけたり、地域で雇用者の合同研修会を行ったりと、危険度の高い人たちを中心に、より的を絞ったケアを行うことができるとの提言がなされていました。
さらに、『白書』では身体疾患、家族不和など自殺の「危機要因」をおよそ68項目に分類、当事者が自殺時に抱えていた危機要因は、1人平均4項目であったことを明らかにしました。それらを踏まえ、危険な状態にある人が、どのタイミングで、どのような支援があれば助かるのか、自殺への危機の進行度を細かく分析し、的確な支援を行いやすいようにすることが大切だと指摘しています。
当事者一人ひとりの抱える問題は千差万別で、それらが複雑に絡み合い、作用し合って自殺へと追い込まれていきます。もし、どこか一箇所にでも助けを求めることができたなら、芋づる式に支援の窓口や専門家につながって解決の手助けとなる......そういうシステムを築いていくことが理想だと、ライフリンクの清水さんは言います。各機関が共通認識を持ち、方針を一元化に近づけることによって、自殺予防のより効果的な実践が可能になるというわけです。
◆キーワードは「セーフティネットの構築」
自殺は、誰にでも、またどの家族にも起こりうることです。身体疾患や経済的な問題はその最たる要因となりますが、重要なのは、そうした「危機」が訪れたときに、果たしてすぐに援助を求められるところが、その人にとってどれだけ存在するのかということです。
小泉内閣以来推し進められてきた構造改革により、弱肉強食ともいえる市場原理主義が日本の社会を席巻しました。その結果、もはや無視できないほどの貧富の格差が出現しています。社会保障や教育・医療も切り捨てが進み、社会の枠組みからはじかれた無数の人たちが生み出されているのです。
昨今、「自己責任」という言葉がさまざまなシーンで使われるようになりました。ある人が会社をリストラされたのは、自分の「努力」が足りなかったせいである。夫からDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けて苦しんでいる女性は、そういう夫を選んでしまったのだから仕方がない......いずれも、自己責任の論理ですが、それでは、敗者復活戦が望めず、一度転落してしまうと二度と這い上がれないということを意味しています。
苦しんでいる人は、すでに自分を十分に責めていることも多いものです。そして苦しみのさなかにあっては、声を上げるのもやっとの状況であるはずです。その人にひとまず寄り添い、今後の新たな道をともに模索してくれる存在が身近にあれば、その人はどんなに救われることでしょうか。
著書『下流志向』のなかで、神戸女学院大学教授の内田樹さんは、上場企業の社員であってもある日突然路上生活者になってしまうという例を挙げ、社会のセーフティネットが機能していないことを指摘しています。かつては、仮に会社が倒産し、解雇されたとしても、親族の共同体や友人たちとの相互扶助、あるいは地縁共同体が何らかの形でセーフティネットとして機能し、とりあえず住む場所や仕事は確保できることが多かったものだと解説しています。
さらに、相互扶助や相互支援というものは、平たく言えば「迷惑をかけ、かけられる」ということなのだから、「迷惑をかけられる」ような他者との関係を原理的に排除すべきではなく、一人ひとりの意識を今いちど見直すことにより、その解決策が開かれることを示しています。
今は元気な人でもそのうち病気になるかもしれないし、いずれは誰もが必ず年をとります。社会全体でさまざまなつながりを断ち切ることなく、地域の共同体をはじめとするセーフティネットを新たに二重、三重に構築していく努力を行うことが、自殺対策への最大の切り札となるのではないでしょうか。
◆まずは身近なところから
シンポジウムにて、前出の清水さんは、自殺対策とはすなわち「生きるための支援」であり、「社会のつながりづくり」であることを強調していました。また、パネルディスカッションに登壇した社会学者の宮台真司さんは、「自殺を減らす=いい社会にする」ことであると発言しています。自殺は、個人の意思や選択の結果だと思われがちですが、実際にはさまざまな要因が複雑に関係して、心理的に追い込まれた末の死でもあるのです。
昨年、全青協は「自殺問題について考えるシンポジウム」を開催しました。そのなかで、僧侶であり、自殺防止の取り組みを行なっているパネリストによる活動報告が行われました。パネリストたちは、悩みを抱える人の相談を受け、地域の人が自由に話し合えるコーヒーサロンを開いたり、インターネット上で自殺志願者の話を聞いたりという、自らの経験を語っていました。
それぞれの形態は違うものの、それらはいずれも「こころの居場所づくり」を行う作業にほかなりません。人間同士のネットワークをつくり、関係性を紡いでいく作業であると言えます。そのネットワークが多くなればなるほど、セーフティネットの網の目が小さくなっていくのは言うまでもありません。
ささやかなことのようですが、まずは家族の、そして、隣の人の言葉に耳を傾けることが必要なのではないでしょうか。人と人とのつながりが希薄になった現代だからこそ、「小さなことの積み重ね」が、今まさに大切なようです。(吉)