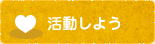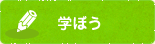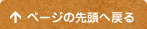仏教者の活動紹介
耳を傾け、全身で寄り添うこと
(ぴっぱら2013年9-10月号掲載)
第37回正力賞受賞者の活動〈青年奨励賞〉 ―浄土宗願生寺副住職 大河内大博さん―
自分がこの世を去るときには、一体どんな状況にあるのだろう。果たして、誰かが看取ってくれるのだろうか......。そんなことは一度も想像したことがないという人は、少ないのではないだろうか。
生を受けたいのちには、必ず死が訪れる。当たり前のことだが、いざ自分がその瞬間を迎えるとき、果たして安らかな心持ちでいられるものだろうか。
全青協附属の臨床仏教研究所が2009年、全国の40〜69歳の男女600人に実施した「お寺と葬儀に関する一般人の意識調査」によれば、「信仰する宗教があることは、死に直面したときに心の支えになると思いますか」という問いに対し、「そう思う」「まあそう思う」と答えた人は70%を超える。
しかしながら「あなたが治癒の見込みがなく、死に直面したら、お坊さんが心の支えになってくれると思いますか」という問いに対して、肯定した人は25%に満たなかった。
この結果が、すなわち仏教の衰退やお寺離れを意味するものでは、もちろんない。しかし、別れの日が近づいていると自覚したその時、心の支えとなってくれるのは、一体何だろうか。
「終末期ケアこそ、仏教者が取り組むべきことだと思いました。でも周囲を見渡しても、驚くほど関心は薄いし、広まってもいない。そんな状況に、危機感のようなものを感じたのです」
大阪市内にある浄土宗願生寺の副住職、大河内大博さんは、学生時代を振り返ってそう語る。大河内さんは20代前半の頃から、病院の緩和ケア病棟等にて、治癒の見込みのない患者さんに対し、こころのケアの活動を行ってきた。
●ビハーラ活動へのきっかけ
国内の医療現場において、こうした活動が宗教者によって行われることは極めて珍しい。その理由としては、医療施設にお坊さんがいるだけで「縁起でもない」と忌避されてしまうこと、そして患者さん側の、ニーズの有無にかかわらず、医療機関の常識として宗教者を受け入れる素地が整っていないことなどが挙げられる。
1979年生まれと若手の大河内さんだが、この分野に仏教者として先駆的に取り組み、後進の育成にも尽力するなど、活動の裾野を広げている。
生家がお寺なので、幼い頃から、いずれはお寺の跡を継ぐことになるだろうと考えていた大河内さん。しかし、お寺や僧侶のあり方を少し違った視点から見てみたいと、大河内さんは仏教系ではない一般の大学に進学した。専攻は政治学だった。
「大学では、『生命政治論』というちょっと珍しい授業がありました。生命倫理に関することを政治的な視点で考えるという授業です。ここではじめて『ターミナルケア』や『ビハーラ』という言葉を知ったのです」
ターミナルケアとは、治癒の困難な患者さんやその家族への、身体的、精神的な終末期ケアのことだ。
また、ビハーラとは聞きなれない言葉だが、もともとはサンスクリット語で「僧院、休息の場、憩いの場」を意味し、ここでは仏教を基盤として、特に精神面を重視したターミナルケアを指す。病を得て、不安感や恐怖感など複雑な想いを抱く患者さんに対して、また、家族を失う悲嘆のさなかにあるご家族に対して、仏教者が直接言葉を交わし、寄り添っていく活動だ。
ビハーラの活動を知り、その有意性にこころを打たれたという大河内さん。一方で、「キリスト教は『愛』というイメージだけど、仏教は『死』って感じだね」と友人から言われ、ショックを受けたのもこの頃だった。
仏教は、亡くなった後だけのものでいいのだろうか。どうせなら、生きているうちから安らぎをもたらすものであるべきではないのか......。そんな思いを強く抱いた大河内さんが、ビハーラ僧になることを決意するのに、そう時間はかからなかった。
大学4年生のとき、大河内さんは日本初のビハーラを行う施設であった、新潟県の長岡西病院ビハーラ病棟に赴く。
●仏教者としての自分を鍛えるもの
ビハーラ病棟では、常勤のビハーラ僧が医療者とチームをつくり、患者さんのケアにあたっていた。大河内さんは、先輩に倣いながら病棟を巡り、毎日患者さんと接していった。
「明日は会えるかしら」と尋ねる患者さんに対し、想いに沿った返事ができず、怒らせてしまったこともある。吐き出さずにはいられない患者さんの想いに、戸惑うことも多かった。
しかし、〝いのち〞の現場に行くからには、傍観者であってはならないという強い思いが、大河内さんを支えていた。
相手と対面するその瞬間、相手のことよりも自分の想いが優先されては、ケアにはならない。マニュアルのない現場で、患者さんのありのままを肯定し、身もこころも捧げてともにあろうとすること。無力である自分自身にも向き合っていくこと。すべては、仏教者としての自分を鍛えてくれるものだった。
大学卒業後も、しばらくは長岡西病院で実践を続けていた大河内さん。地元の大阪にもビハーラを広めたいと、2003年、協力者とともに、後にNPO法人化する「ビハーラ21」を立ち上げた。そこではビハーラ僧としての個々の活動を推進するほか、僧侶や医療者などビハーラを行う人材を養成するためのプログラムとして、勉強会や研修会を定期的に開催した。
また2011年には、より臨床に特化した活動がしたいと、新団体「いのち臨床仏教者の会」を立ち上げた。ここでは、死別体験者の分かち合いの会を開催したり、臨床現場で活動する仏教者がそれぞれの悩みや情報を共有できる、相互ケアの会を企画したりと、活動者とケアの対象者、双方のニーズに即した活動を展開している。
●他者の苦しみに関心を寄せて
「僧侶としての自分自身のあり方を見つめるためにも、臨床の現場にいなければという思いが強くあります。ビハーラの活動を行う際にも、はじめはお坊さんの格好をすることにこだわりがありましたが、最近は、そう思わなくなりました。患者さんと向き合う時、衣を着なくても僧侶であることは伝わるし、逆に言えば、お坊さんの格好をしていてもきちんと向き合えていなければ、お坊さんである意味がありません。患者さんには、すべてお見通しなんです」
現場では、用意した言葉や教科書どおりの対応は通用しない。限界あるいのちを持つ人間同士が、時間を共有して、全身で問いなき問いに耳を傾けること。難しいことだが、誰かがやらねばならないことであり、これこそが宗教者に課せられた使命ではないかと、大河内さんは考えている。
高齢化が進む中、医療現場は多忙を極めている。一人ひとりのこころに寄り添うような手間のかかるケアは、十分になされているとはいえないのが現状だ。また、現場で働く医療者も人知れず心労を重ね、精神的に疲弊している場合が少なくない。こうした声は届きづらいものだが、だからこそ、仏教者には世の出来事にアンテナを張りめぐらせていてほしいと、大河内さんは訴える。
「僧侶がいつもお寺にこもっていたら、社会の苦しみに出会うことができないでしょう。僧侶として一人前になるために、こうした活動がどれほど私たちを磨き、鍛えてくれるかわかりません。仏教者が社会に出て行って臨床的な活動を目指したとしても、お寺の中で何らかの活動を行っていくとしても、どちらでもいいと思うのです。お寺にとって社会活動が、もっと当たり前になるといいなあと思います」
2500年前のお釈迦さまの時代であっても、科学が発達した現代であっても、この世の苦しみである「老・病・死」、そして、愛する人と別れなくてはならない苦しみからは、誰もが逃れることはできない。こうした現実を前に仏教者ができることは、マニュアルどおりの言葉を並べることではないはずだ。
目の前の苦しみに関心を寄せて、我がことと思い、向き合う覚悟が、社会に生きる仏教者にいま求められている。