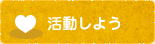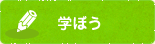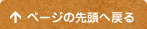仏教者の活動紹介
口演童話と紙芝居でこころを育む
(ぴっぱら2009年11-12月号掲載)
第33回正力賞受賞者の活動 ―西山浄土宗常福寺 畑崎龍定―
●疎開中の子どもたちを前にして
JRきのくに線の南部駅に降り立つと、磯の香に混じってほのかな梅の香が漂ってくるような気がする。和歌山県の中西部に位置する日高郡南部町は、太平洋岸に面した港町であると同時に全国有数の梅の産地でもある。ここで収穫された梅は特に南高梅として全国に知られ、高級品として各地に出荷されている。
この自然豊かな町で、畑崎龍定さんは60年余りにわたって老若男女を対象に、口演童話と紙芝居を続けてきた。そのきっかけとなったのは、本山光明寺での修行時代の体験であった。昭和19年に旧制中学を卒業した畑崎さんは、同年京都長岡京にある本山運営の専修学校へと進学する。
昭和20年になり都市部の空襲が激しくなると、京都深草小学校の子どもたちが本山へ集団で疎開をしてきた。
「親と離れて寂しかったんでしょうね。夕方になると子どもたちが家へ帰ろうと脱走するんですよ」畑崎さんたち学生は、逃げた子どもたちを捜して寺に連れ帰った。
「そんな子どもたちを見ていて、自分が何ぞできんやろかと思ったんです」
仲間で相談し始めたのが、仏教童話の読み聞かせだった。毎晩夕食後に100人ほどの子どもたちを前に交代で話をした。ほどなくして紙芝居も作るようになり、子どもたちに大人気となる。そして、脱走する子どももいなくなった。このことがきっかけとなって、60年余りにわたる口演童話と紙芝居の歴史が始まる。
●はまゆう子供会
終戦後の昭和22年3月に専修学校を卒業し自坊の常福寺に戻ると、畑崎さんは小学校の教員を務めながら、寺での活動にも力を入れるようになる。本山での経験を生かして、今日まで62年間続く「はまゆう子供会」を始めた。今でも毎月30名ほどの参加者を得て開催されているが、昭和40年代の最盛期には、毎回100人以上もの子どもたちが集まったという。
子供会のプログラムは、「賛仏歌」「般若心経」「ほとけさまの教え(全青協制定)」を唱和することから始まる。そして、墓や地蔵堂などの清掃を分担で行った後は、いよいよお楽しみの紙芝居だ。仏教説話や宗祖の話、郷土の偉人伝などレパートリーは20以上にもなる。
畑崎さんは紙芝居のことを「絵話し」と表現する。自分でストーリを構成し、自分で絵を描いて、自分で語る。1作を平均1週間ほどで描き上げるという。「テーマが決まるとつい夢中になって、車を運転していても、絵話しの構成のことで頭がいっぱいになるんです......」と笑う。
各地の子ども会や高齢者、婦人会の集まりで実演することも多い。その功績が評価され、平成12年には、口演童話の先駆者であり、日本のアンデルセンとも呼ばれる久留島武彦にちなむ文化賞も受賞した。
●鯉のぼりを上げない村
4月の花まつりの時期には、子ども向けに「平家祭り」を開催するようにもなった。平家祭りとは、昔この地に隠れ住んでいた平家の落人たちの非業の死を悼み供養する行事である。畑崎さんはその伝説を紙芝居にして毎年子どもたちに語り伝えている。
その手作りの台本の出だしは次のようなものだ。
「若葉香る5月、南紀のあの町この村でも鯉のぼりが青い空に泳ぐようになります。ところが昔から五月の節句がきても鯉のぼりを上げない土地があります。それは紀伊半島の中央にある日高郡みなべ町の堺地区です。それには次のような伝説があるからです。
今から800年余り前の昔のことです。その頃日本の国には平家と源氏という二つの勢力の強い武士の集団がありました。平家のしるしの旗は赤、源氏のしるしの旗は白でした......」
話の要旨はこうだ。
源平の戦いに負けた平家の落人たちがこの地に移り住んだ。村人の中にすっかりとけ込んだある年の5月、もう追っ手も来ないだろうと安心した落人たちが、子どもたちのために平家のしるしの赤旗を浜辺の松林に立てた。すると沖合から陸を監視していた源氏の追っ手がこれを見つけ、村人たちの命乞いも聞かずに落人たちを皆殺しにしてしまった。以来、堺の人たちは落人の無念を忍び、節句のときに鯉のぼりを上げないのだという。
常福寺では、鯉のぼりの代わりに平家のしるしである赤旗を上げている。なぜ花まつりの際に、平家祭りを一緒に行うようになったのだろうか。畑崎さん聞いてみると、次のような答えが返ってきた。
「花まつりはお釈迦さまの誕生を祝うもので、いのちを大切にすることを子どもたちに伝えるものです。平家祭りも目的は一緒なんですよ」
生と死というコントラストを浮き彫りにさせながら、畑崎さんはいのちの大切さ尊さを子どもたちに伝えようとしているようだ。
「戦争中には出征兵士が空の白木の箱に入って帰って来るのをよく見ました。今の子どもたちは豊かな社会の中で育っているので、生きていることの幸せさを実感することがありません。死とふれ合う機会がなくなってしまったんですね」
平家の落人の話ばかりでなく、自身の戦時中ひもじかった頃の話や、漁で亡くなっていった人たちの話もあえてするという。「死を身近なものとして伝え、生命の尊さを伝えることが大事」という思いが、畑崎さんの子どもたちに対する情操教育の一つの柱になっている。ただ、現代社会の中では「子どもたちよりも親の方がより心配」だと言う。
「学校で教師が子どもをしかると、すぐに親が教育委員会に駆け込みます。自分の子どもしか見えていないんですね。親には簡単になれますが、賢い親が少なくなってしまいました」これからは、子ども会ばかりではなく、「親育」の会をお寺で開催する必要があるのかもしれない。
●時代を超えて
畑崎さんが描く紙芝居の絵の裏面はどれも真っ白だ。台本はすべてご本人の頭の中に入っている。「話を聞いてくれる人たちの表情を見ながらアドリブを交えて進めて行く」のが、絵話しのスタイルだそうだ。一期一会、対機説法ということなのだろう。老若男女を問わず対象として実演できる秘訣がそこにあるのかもしれない。
テレビゲーム世代の子どもたちの反応はと聞くと、「はじめは退屈するのではないかと思いましたが、子どもたちの目を見ながら話しをするとみんな真剣に聞いてくれます」と微笑みながら答えてくれた。
「今の若い青年僧にも、ぜひ青少年の教化活動に関わってほしいと訴えているんですよ。子どもの頃からのご縁が将来につながって行きますからね」
社会の風潮がデジタル化する中で、口演童話と紙芝居というアナログな媒体は、子どもたちにとって目新しいものなのかもしれない。というよりも、時代を超えてアナログな皮膚感覚の媒体を、人は求めているということなのだろう。
そんな畑崎さんの思いを受け継ぐアナログな青年僧が、一人でも多く育ってくれることを願ってやまない。