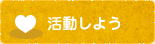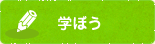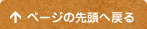仏教者の活動紹介
絵筆と数珠を携えて ―千蔵院―
(ぴっぱら2005年7月号掲載)
さあて、むかしむかし......
夕方の公園の片隅に、自転車を押したおじさんが現れると、小銭を握り締めた子どもたちがバラバラと集まってくる。そして、「さあ今日も、紙芝居の始まり始まり」――戦前から戦中・戦後にかけて、日本のあちこちで見受けられてきた光景だ。しかし、このような街頭での紙芝居は、テレビが普及しだした1960年代ごろを境に衰退し、今の子どもたちはもはや知る由もないに違いない。
もし、あの頃のわくわくする気持ちを思い出したければ、新潟県長岡市を訪ねよう。中越地震により被災し、復興に励む街の中でも、被害が比較的小さくて済んだ地域がある。その郊外地に建つ真言宗豊山派千蔵院に行けば、畳ほどもある大きな紙芝居を楽しむことができるはずだ。そして、大勢の子どもたちを前にして、穏やかな風貌で熱演するお坊さんに出会うことだろう。
ここで見ることができるのは、懐かしの「黄金バット」でも「少年タイガー」でもない。地獄のお話や、お釈迦さまの前世の話など、仏教にまつわるお話ばかりだ。内容は違っても、紙芝居の前に集まった子どもたちはあの頃と同じ、輝くような目で見入っている。
自分の夢と仏教と
熱演を見せてくれるのは、副住職の諸橋精光さんだ。千蔵院の長男として生まれたものの、後継ぎとしての将来よりも絵の世界への情熱が深く、高校卒業後は美術の道を目指した。上京し、美術専門学校を経て大正大学に入学する。しかし、住職である父の体調が思わしくないこともあり、1982年に帰郷した。
一度は志した芸術の道。生まれ育った環境の中で、また大学の学びの中で出会った仏教の道。帰郷により、どちらも中途半端になっていると感じて悩む日々が過ぎた。寺にいると、100号キャンパスを前にしていても、頻繁に訪れる来客に、たびたび絵筆を置かざるを得ない。そんな暮らしは、絵にも法務にも集中できない諸橋さんのこころをふさいでいった。
そんな諸橋さんに転機を与えたのが、毎年寺で行われていた夏祭りと、集まってくる子どもたちだった。毎年恒例の夏祭りに合わせ、諸橋さんが自坊に戻った年の夏から、子どもたちを対象にした「子ども祭り」も企画したのだ。お菓子を用意したこともあって、200人以上の子どもたちが集まった。
しかし、集まる子どもたちに、ただお菓子をあげるだけではつまらない。夏祭りの際には本堂に地獄・極楽図が掛けられる。それにちなんで、集まる子どもたちに絵解きをすることを思いつく。なにしろ200人からの子どもたちだ。普通の画用紙などではとても見えないし、見てもらえない。できるだけ大きな絵でなくては......。
「いっそ、10畳くらいの大きなものがいいと思いました。さすがに大変なので、後からあきらめましたが」と諸橋さんは当時を振り返って笑う。
そんな折、檀家参りの途中で段ボール工場を通りかかった諸橋さん。「段ボールだ!」その大きさに、これに絵を書こうとひらめいたのだ。
美術の世界では、大きな作品を描く際、まず全体の構想を考え、作業の手順や表現効果を検討するために、エスキースと呼ばれる縮小版の作品を作ることがある。美術学校時代、エスキースの段階では段ボールに描くことが多かったので、諸橋さんにとってダンボールは画材として突飛なものではなかった。こうして、段ボールに描かれた大きな紙芝居が生まれることになった。
活動の広がり
あるとき、宗派の青年会の集まりがあり、そこで話すうちに、大正大学の演劇部出身者と知り合った。彼の協力で、段ボール製の紙芝居が、ドラや太鼓で効果音の入った、より生き生きとした語り芝居へと成長を遂げ、物語に魂が吹き込まれていった。
子ども祭り当日は、本堂の地獄絵図をモチーフにした物語ということもあり、怖いもの見たさで子どもたちが大勢集まり、聴き入った。幼い子の中には泣き出す子どもも出るほどだったという。子どもたちの反応の良さに、仏教と芸術の狭間で揺れていた諸橋さんの迷いは消えていった。
こうして、翌年からはさまざまな仏教説話を題材に、紙芝居を製作していった。お釈迦さまの前世物語と言われる「ジャータカ」や日本の「今昔物語」、仏典の中のさまざまな説話......。仏教の世界には、ただの教訓話にとどまらない、すばらしい物語が宝箱のようにあふれていた。それらを僧侶の視点からかみくだき、再構成して、諸橋さんは子どもたちに伝えやすい絵本や紙芝居にして次々に発表していく。毎月の観音様の縁日には、10ページほどの小さな絵本を施本として配布しており、また、諸橋さんに転機を与えた夏の子ども祭りでの紙芝居も、恒例となって毎年続いている。
諸橋さんはいまや、紙芝居だけでなく絵本作品も多く出版し、世界から3000点の作品が集まる国際絵本原画展に出品・入選するなど、日本にとどまらず海外でも評価される画僧として活躍している。
子どもの中の光に目を向けて
講演先や子ども祭りで出会う今の子どもたちをどう見ているか尋ねると、諸橋さんはこんなエピソードを話してくれた。
「先日、市内でも有名な荒れた高校で、紙芝居の実演をしたのです。彼らに紙芝居が通じるのかと不安でしたが、二作品を演じる間、じっと見入ってくれていました。先生方も『子どもたちがあんなにじっとしていることはめったにない』と言っておられたくらいでしたよ。子どもの中には、今も昔も変わらず子どもらしい、純粋な部分があるのです。そんな、子どもの中の光に、これからも紙芝居を通して発信し続けていきたいですね」
環境の中で身につけたほとけのおしえと、志した芸術の世界での感性の双方が揃えばこそ、子どもの中の光を見抜くことができる。数珠をつけた同じ手で絵筆を握る諸橋さんだからこそ、その光に届く物語をつむぎ続けることができるのだろう。
魅力と可能性を秘めるもの
昨今、教育現場などで紙芝居は見直されつつあるという。日本だけでなく、アジアでも教育現場で使われ、地雷の危険性を子どもたちに伝えるなど、大切な役割を果たしているという。「紙芝居は、日本独自の文化です。私は、この表現方法にはまだまだ魅力と可能性があると思っています」と話す諸橋さん。テレビやインターネットにはない一体感や双方向性を持つ紙芝居は、古臭いと思われがちだが、確かに魅力と可能性に満ちている。仏教もまた然りなのだと、諸橋さんの絵の中の小僧さんが微笑みながら語りかけてくれた。(渉)