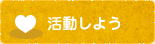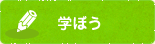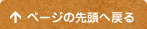仏教者の活動紹介
人と人はつながっていく ―常光寺日曜学校―
(ぴっぱら2003年8月号掲載)
炭坑の町で始まった日曜学校
北海道美唄市。大都市札幌と旭川のほぼ中間に位置するこの町は、明治時代に騎兵屯田兵によって開拓され、その後は北海道有数の炭鉱(ヤマ)の町として道内外に知られるようになった。最盛期には、中心の我路と呼ばれる地域だけで関係者3万人以上を数え、病院や学校をはじめ、商店街や映画館・劇場などの娯楽施設もあったという。
明治から昭和まで、日本の経済発展を支えた北限の町である。
杉田英明師がこの町に生まれたのは昭和5年のこと。父親は布教師として大正8年にこの町へ入った本願寺派の教師だった。説教所から始まり、昭和4年に我路に一寺を建立する。生まれ故郷の福井から、育った青森を経て、「信」の確立を目指しながら北海道へと渡った気骨ある明治の人だった。
児童教化にも熱心だった父親の影響を受けてか、杉田師は京都の龍谷大学に入ると、すぐさま宗育部に所属する。そこで身につけた、影絵劇やペープサートなどの技術をもって、京都の寺で開かれる子ども会に頻繁に参加した。そして大学卒業後、北海道に帰った杉田師は、昭和36年に現坊守の琉子さんと結婚する。
「結婚を機に、二人が寺で何か活動できることがないかと考えましてね。やはり日曜学校が良いのではないかということになったんです」と、杉田師は日曜学校を開設した理由について語る。琉子さんも旭川の寺育ち、やはり子どものころから日曜学校に慣れ親しんできた。「当時は何もない時代だったので、日曜学校で紙芝居を見たり、童話を聞いたりすることがとても楽しみだったんですよ」と、朗らかに語る。二人の思いの中に迷いはなかった。
さっそく杉田氏は、大学の影絵劇研究会の指導書をもとに、芥川龍之介の「杜子春」を製作する。門徒の婦人会の女性たちが協力してくれ、大勢の子どもを集めてくれた。以来、毎週日曜日に子ども会を開催し、最盛期には101人が登録していた。「夫婦ともにとても楽しい時期だった」と往時を振り返る。
子どもがいなくなる
しかし、ほどなくして常光寺日曜学校に試練のときがやってくる。その大きな原因は、昭和47年の三菱美唄炭鉱閉山であった。その予兆はすでに結婚の翌々年、昭和38年の三井美唄炭鉱閉山に見られた。最盛期は2万近くあった町の世帯数が徐々に減り始め、当然のことながら子どもの数もどんどん減っていった。炭鉱の人たちは、新たな職を求めて札幌や函館などの大都市へ移り住み、本土へと旅立つ者も少なくなかった。美唄の町が大きく変わった。
常光寺も昭和48年に市内の中心部に近い東明に土地を求め、新たな布教の場として東明会館を建設した。米寿を迎えた先代と、夫を失った姉がここに移り住んだ。しかし、やがて平成を迎えるころ、杉田師も慣れ親しんだ我路の地を後にし、常光寺の寺基移転を決断する。寺の存続、そして日曜学校の存続を考えると、止むを得ない判断であった。
移転してからは、日曜学校へ通ってくる子どもたちの顔ぶれも変わった。子どもたちの中心は、中学生になった長男の同級生たちだった。彼らが高校へ進学するころになると、寺には子どもがまったく集まらなくなった。平成7、8年のこと、日曜学校の存続が危ぶまれた時だった。
「地域の人たちと顔なじみになるまでに時間がかかりました」と琉子さんは語る。
あるとき二人は意を決し、門徒の家へ頼みに行くことにした。
「お子さんたちを日曜学校へ通わせてください」
頭を下げながら二人は家々を歩いた。
ある門徒さんが、兄弟姉妹3人を出してくれた。やがて、その友だちも少しずつ集まってくるようになった。なんとか日曜学校の体裁が保てるようになった。しかし、29年間続いた毎週日曜日の開催は、月一回の開催となった。
OBたちの支え
新たな企画として、住職は、寺の境内で盆踊りを始めることにした。かつては町会の主催で行っていたものだ。一人、住職は手作業でやぐらを作った。地道な作業が続いた。
まもなく、住職の姿を見ていた日曜学校のOBたちがやってきた。そして、「おれたちが作ってやるよ」と、鉄パイプでやぐらを組んでくれるようになった。そればかりか、盆踊りに必要なさまざまな備品までも持ち寄ってくれるようになった。町一番の焼き鳥の屋台も出るようになった。
かつて小中学生のころに日曜学校に通っていた子どもたちの「日校OB会」が誕生した瞬間だった。中心メンバーは、すでに30代から50代になっていた。住職夫妻は、「日校を続けていて本当に良かった」と、しみじみと30年余りの月日を振り返った。
OBたちが主体となった常光寺の盆踊りは、今年で10回目を迎える。そして月一回となっていた日曜学校も、彼らの尽力もあって、隔週の土曜学校へと衣替えをした。消えかけていた子ども会の光が、再び明るく輝き出した。
「子ども会を続けてきて嬉しかったことは?」と、ご夫妻に聞くと、まず住職は「生きていることの楽しさを共感し、本音の付き合いが子どもたちとできたときですね」と答えてくれた。そして坊守さんは、「生きることが苦しくなったときに、日曜学校のことを思い出してお寺へやって来てくれる人がいます。そんなかつての子どもたちと会話を交わすことができたとき、続けてきて本当に良かったなと思います」と、しみじみ語ってくれた。
数年前のことだが、上流にあるダムに身を投げようとした女性がいたそうだ。彼女は常光寺日曜学校の卒業生だった。寒さの中で凍える中、かつて通った日曜学校のことを思い出し、死の淵から戻ってきた。そして、寺地を変えた寺をわざわざ訪ねてきたという。
少年による悲惨な事件が続く昨今、「子どもたちに一番伝えたいことは?」と問いかけると、「温かな深い目、他人の苦しみや痛みに共感できる心を、子どもたちと一緒に味わっていきたいと思います。時を経ても変わることのない、仏の慈悲の心を感じあえるような有り様をこれからも模索していきたいですね」と、住職が答えてくれた。夫妻の目線は、いつも子どもたちと同じところにあるようだ。それが、心と心のつながりを生む秘訣なのだろう。(神)
常光寺日曜学校
北海道美唄市東明二条三丁目一ノ十二