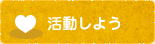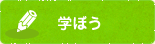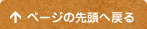仏教者の活動紹介
弱者と寄り添う中で ―プラパートナンプ寺院―
(ぴっぱら2003年4月号掲載)
エイズ患者に寄り添って
タイのみならず、いまやアジアの玄関口となっているバンコク。そこから、有名な遺跡のあるアユタヤを越えてさらに北へ向かうと、ロッブリーという街にたどり着く。アユタヤほどではないが、遺跡の街として知られるこの地の郊外にあるのが、プラバートナンプ寺院だ。バンコクなどのきらびやかな観光寺院とはイメージが異なり、広々と開かれた中に、質素な建物が寄り添いあっている。しかし、目立たなくても、こここそが、タイで最初に開かれたエイズホスピスとして、タイのみならず諸外国にまで存在が知れ渡った寺院なのだ。
タイ人の上座部仏教僧侶、アロンコット師が、この寺院にエイズ患者を受け入れるようになったのは1992年のことだ。
タイを中心にした東南アジア一帯では、ここ十数年、HIV/AIDSが蔓延している。症状や予防法など病気に対する知識が一般に不足しているため、家族や地域の偏見の目にさらされることを恐れ、多くの患者が、治療はおろか感染していることすら口にできないまま病と闘っている。そんな彼らが、貧困苦や病気への知識のなさなどから売買春に手を染めてしまえば、感染はさらに拡大していく。
病に苦しみ、同時に偏見や貧困による孤独にも苦しみながら息絶えていく患者たちと出会ったアロンコット師は、彼らに寄り添う中で、やがて一人ふたりと患者を寺に迎え入れていく。そこから、現在のホスピスへと発展していったのである。
仏教を基として
タイなどアジアの仏教は、一般に上座部仏教と言われる。大乗仏教と言われる日本や中国の仏教とは異なり、出家した僧侶は自らの悟りや解脱を求めて修行し、在家者は出家者にタンブン(喜捨)をすることで徳を積み、来世での幸福を願う。
そんな宗教土壌の中で、出家者である僧侶が俗世の社会問題に向き合い、在家の人々のために活動することは、当時はとても珍しかった。最近、「他の人々も救済されてこそ、自らの解脱もある」という発想から、社会活動を行う「開発僧」と呼ばれる上座部の僧侶も増えてきてはいるが、アロンコット師がホスピスを始めた当初は、出家者が世事に関わるということが受け入れられず、出家者・在家信者双方から反発があったという。しかし、アロンコット師の深い思いが、しだいに人々の反発心を溶かしていった。
現在寺院にいる僧侶のうち、およそ8割がHIV感染者である。ここに来てから出家した患者も多い。そんな事実も、アロンコット師の思いが結晶したひとつのあらわれなのかもしれない。
人々とともに
現在、ここではおよそ200人の患者が暮らしている。さらに近所に1000人ほどが暮らす施設があり、その中には、親をエイズによってなくして孤児となったり、あるいは母子感染でエイズキャリアとして生まれた子どもたち、およそ400人が含まれている。
運営は74名のスタッフの手で行われており、最先端医療のみならず、ハーブなどを利用するタイの伝統的な医療も活用した治療が施されている。ヨーガや瞑想をとり入れるなど、仏教を基としながら、患者本人だけでなく、家族を含めて「心と身体を強くするケア」をしているのだという。これまでにおよそ1万人の患者がここでケアを受けてきた。
現在、ホスピス運営に関わる資金は、政府からの補助金として年100万バーツ(およそ280万円)と患者たちが作るクラフト製品の販売がもたらすささやかな売上金の他は、ほとんどが寄付金でまかなわれている。
治療など、ここで患者たちが受けるサービスはすべて無料で提供される。組織がこれほど大きくなった今、アロンコット師は資金集めに東奔西走する日々だ。
ここで提供されているのは治療だけにとどまらない。涅槃会などには行事も行われるし、バスケやサッカーもする。患者から生まれたバンドもあるのだという。症状の軽い患者は、掃除などできる範囲で仕事もする。単に「世話される者」として庇護されるだけではない、自立した関係性がそこには見受けられる。
また、患者へのケアのみならず、小中学校やメディアに対するHIV教育も行っている。少しでも知識を広めることで、しなくていい感染が少しでも防げるようにということはもちろん、患者に対する偏見をなくそうという意図もそこにはある。
いずれにせよ、ここにあるのは、「死を迎える施設」という言葉から想像される、重苦しい雰囲気だけでは必ずしもないのだ。
死と向きあう
しかし、毎日数人が亡くなっていくという現実の中、死に目を背けていることはできない。
プラバートナンプ寺院を訪れる見学者が誰しも衝撃を受けるのが、寺院内にある施設「After Death Room(死後の部屋)」と「Bone Museum(遺骨博物館)」だ。「After Death Room」には、AIDSによって亡くなった人の遺体が裸で保存され、展示されている。本人から生前に「エイズの恐ろしさを人々に伝えるために」と献体を申し出ていたのだという。
生き生きとした生前を偲ばせる遺影と、文字通り骨と皮になるほど痩せ細った遺体。それらがかつて同一人物のものだったとは、とても想像ができない。遺体が女性であるがゆえにその衝撃はより深く、伝わってくる故人の強い思いに、言葉を失うほかない。
「Bone Museum」もまた、強烈な無言のメッセージに満ちている。このホスピスで亡くなっていく患者の多くは、帰る場所を持たず、還る家族を持たない。そのため、亡くなった患者は、敷地内にある火葬炉で荼毘に付されると、小さな箱や袋に納められた遺骨となってこの部屋に帰ってくる。まさしく山となった遺骨の袋や箱。それぞれが、かつては確かに生きた「いのち」であったことに、不思議な畏敬の念がわき、自ずと手の合わさる思いがする。
ここでは、「死」が常にむきだしにされて突きつけられており、否が応でもそれと向き合わざるをえない。死は人に等しく与えられた宿命ではあるのだが、エイズという病の周辺にとりわけ重くのしかかるテーマなのだということを、遺体や遺骨となった彼らは、無言で私たちに訴えかけている。
人生とは何か
施設を案内してくれたスタッフに、ここで学んだことは何かと尋ねると、「人生とは何か」だという答えが返ってきた。長く生きることにどんな意味があるのか。よりよい生とは何か。人は人生から何を学ぶのか。そういった、哲学とも、生き方とも言える何かを、ここでは常に考えさせられるのだという。
常に死を目の当たりにし、死と向かい合って暮らすのがホスピスだ。仏教を基にしているこのプラバートナンプ寺院にいるからこそ、答えのない問いに向かい合う勇気が持てるのかもしれない。そんな勇気が、ここで育っていく孤児たちにも伝えられていくことを願いたい。(内)